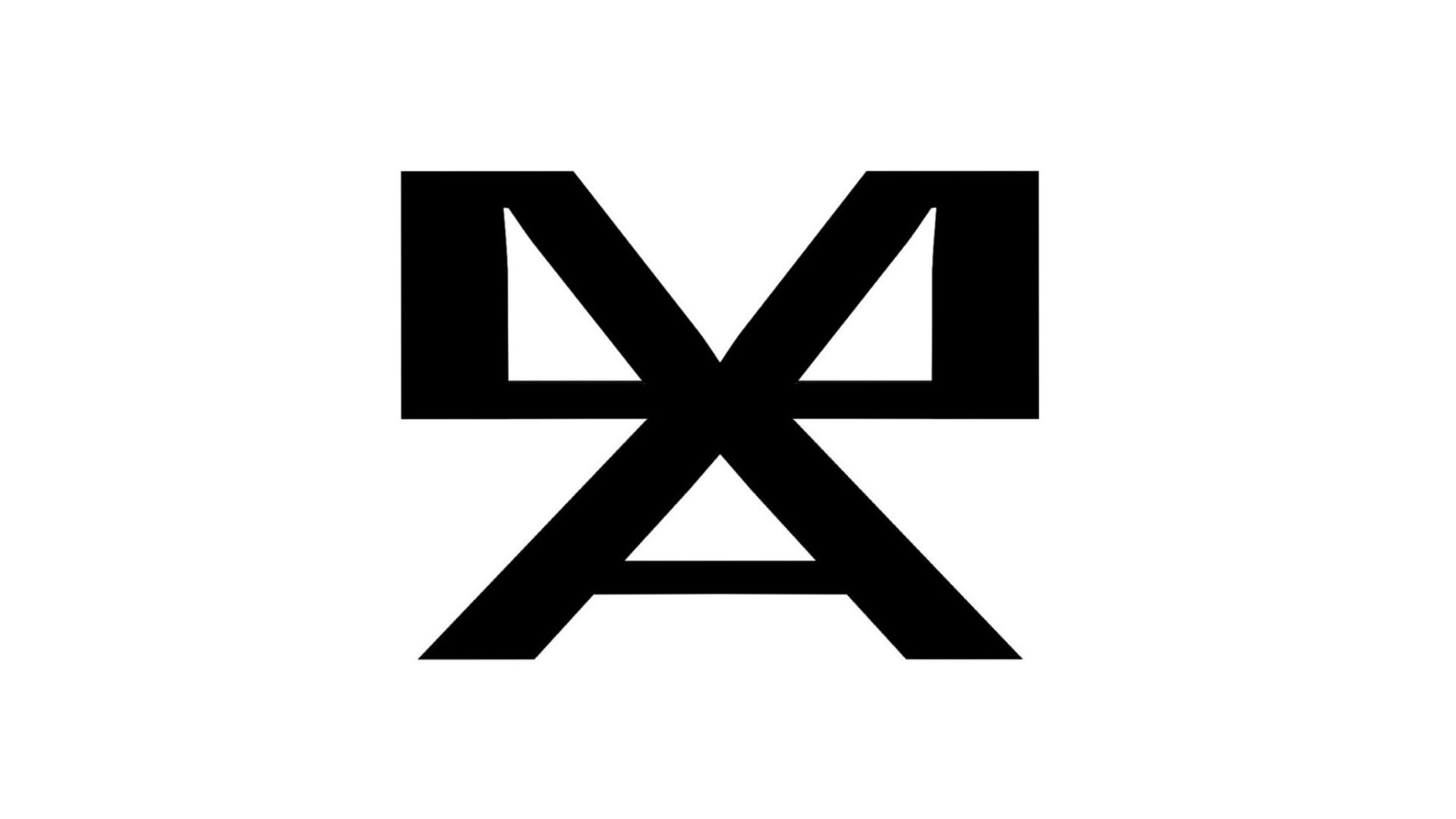事業譲渡での「のれん」のメリット
株式譲渡と事業譲渡では財務面でも違いがあります。税に関しては、個々の取引で複雑な処理が求められますし、税制の変更もありますから、ここでの解説は概念的なものととらえてください。実際の税務処理のときは税理士さんに相談して進めてください。
まずは「のれん」の取り扱いの違いです。会社は通常、純資産に一定額を上乗せして買い取ります。本来、その会社の価値は、貸借対照表に載っている純資産分ですから、上乗せした分については、その会社に、それを上回る価値があると評価したことになります。会計的にはその部分をのれん資産として扱い、BSにものれん資産として表記します。
のれん資産は減価償却できることになっています。ということは、毎年、その分の費用が増え、結果として税金が減ることになります。
ただ、こうしたのれん資産の扱いができるのは事業譲渡のケースだけで、株式譲渡ではできないルールとなっています。それがなぜかは、BS上での取り扱いで見ればわかります。
事業譲渡では、その事業は元の会社のBSから新たな会社のBSに移ります。そのとき、その事業は純資産分より市場価値が高いと、他者から評価されたことが確定します。ですから、その分はのれん資産としてとらえることができるのです。
一方、株式譲渡ではBSそのものの持ち主が変わるだけです。BS上は資産の移動も他者評価もありません。ですからこのルールが使えないのです。
関連記事→簿記を学ぼう(BS編)
つまり、同じ金額で同じものを買っても、スキームの違いで税金が変わってくることになります。
株式譲渡では譲渡益課税にメリット
売り手側への譲渡益課税でも違いが出ます。売り手が法人の場合は、株式譲渡でも事業譲渡でも法人税率が適用され、その課税率はおよそ30%です(法人税率は、法人所得などによって変わりますが、ここでは便宜的に30%とします)。
しかし、個人所有の株を株式譲渡する場合は、キャピタルゲイン課税の扱いとなり、その課税率が適用されて、元オーナーにかかる課税率はおよそ20%になります。
たとえば、課税額が1億円なら、スキームの違いで課税率が10%上がれば、税額は1000万円上がりますから、その違いは無視できないでしょう。
つまり、この取引に対する課税率は、その会社を事業譲渡で買えば約30%ですが、オーナー個人所有の株を株式譲渡するスキームにすれば、10%下がって約20%の課税率になるということです。となると、「事業譲渡でなく株式譲渡を選ぶ代わりに、税金が減る分に見合う額を値下げしてほしい」という交渉もあり得るわけです。
関連記事→違いについての詳しい記事はこちら
繰越欠損金では株式譲渡にメリット
繰越欠損金もスキーム選択の材料になります。繰越欠損金とは、赤字を一定期間、損失として貯めて込んでおけるという税制上のルールです。繰越欠損金があれば、経営が黒字に転換しても、利益が繰越欠損金分を上回らない限り、税金を払わなくていいというものです。
株式譲渡の場合は、この繰越欠損金も丸ごと引き継ぎます。買収対象の会社が1億円の繰越欠損金を計上していたとすると、買収後、黒字になっても、利益が1億円を超えない限り、税金を払わなくていいことになります。
一方、事業譲渡では、この繰越欠損金は引き継ぐことはできません。繰越欠損金の節税メリットは得られないということです。
取得税でも株式譲渡にメリット
もうひとつ、税制面で、株式譲渡と事業譲渡で大きく変わるのが取得税です。株式譲渡では株の所有者が書き換わるだけなので、取得税は関係ありませんが、事業譲渡では買い取ったものによっては取得税がかかるものがあります。
たとえば土地です。土地を買い取れば、不動産取得税、登録免許税がかかります。建物や設備、在庫、のれんにも消費税はかかります。これらが意外と嵩むので注意しましょう。
たとえば、土地500万円、工場設備1500万円、合計2千万円を事業譲渡で引き継いだとすると、土地に対する不動産取得税4%で20万円、登録免許税2%で10万円と、工場設備に対する消費税10%の150万円がかかります。2千万円の事業譲渡に対して、(あくまで概算ですが)180万円の納税が必要になるのです。
私も初めて事業譲渡をしたときは、取得税の額の大きさにいささか驚きました。ただし、還付制度があるので、実際の負担額は変わってきます。
再度お伝えしますが、ここで述べたのは基本的な考え方についてです。実務上では、さまざまな税制があって、取り扱い方が変わったり細かな数字が違ったりしますので、実際にどうなるかは、税理士さんに確認しながら進めてください。
続いてのコラムから、会社の値段を決めるプロセスの解説に入ります。
記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)
2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。